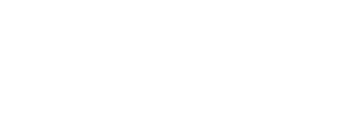特別講話
「地域産業や子供神楽(かぐら)を広める宇佐八幡ゆかりの氏神様」 郡山八幡神社
郡山八幡神社
宮司/上本 博之 氏
特別講話ダイジェストムービー(郡山八幡神社)

- ─郡山八幡神社はもともと違う場所にあったと伺いました。
- 東大寺大仏殿造立の際、九州の宇佐神宮から勧請(かんじょう)した八幡神を分祀(ぶんし)し、現在の郡山城跡公園の北西に位置する小高い土地に祀(まつ)ったのが最初とされます。文献で確認できるのは室町中期頃だそうですが、社伝では創建はもう少し早い時期であったと伝わります。後に豊臣秀長公が郡山城に入られるとき、城を大きく強いものにするにあたって当社は遷座(せんざ)しました。一度大和郡山市内の「綿町」に遷ってから現在地に鎮座したようです。最初の小高い場所は「柳」という地域で、今当社がある地も「柳」という地名となり、「柳八幡宮」とも呼れています。
- ─「グラブ神社」としても知られておられますね。
- 10年程前になりますが、近鉄郡山駅近くにあるグラブ工房さんがご参拝においでになったことをきっかけに各所から不要になったグラブを当社に納めていただいて、海外の子どもたちに贈る活動をしています。東北で震災が起こったときには、現地の子どもたちにもお届けしました。子どもたちには元気いっぱいに遊んでほしいですね。八幡様は勝負の神様なので必勝祈願やプレーの上達を願ってのご参拝も増えました。以前はグラブ祭という行事をしていましたが、コロナ禍以降中止しています。あのときに途切れたものもあるので、今からまた急がず、たゆまず、ゆっくりと紡ぎ直していかなければと思っているところです。
- ─例えばどういったことを紡いでいきたいとお考えでしょうか?
- 地域のお子さんに集まってもらい、巫女さんのお稽古をしてもらっています。こちらもスタートして10年ほどの取り組みで現在も続いています。当初は幼稚園生や小学校の低学年だった子たちが大きくなり、夏祭りや秋祭りのときなど拝殿で美しく神楽を舞ってくれます。ただ次世代につなげるのは難しいですね。でも、続けてくれている子たちは「お神楽が楽しい、舞うのが楽しい、お稽古が好き」と言ってくれています。そういう気持ちを地域の皆様と一緒に、この場所で後世に引き継いでいけたらうれしいですね。そうそう、本殿と拝殿の間に安置する狛犬が江戸初期頃の木製で少し珍しいものだそうです。そうしたこともお伝えしていきたいです。

プロフィール
郡山八幡神社/宮司 上本 博之 氏(うえもとひろゆき)氏
1968年奈良県生まれ。奈良教育大学を卒業し小学校教員を勤めながら禰宜として父である宮司を補佐。2009年教員を辞し宮司に就任。「神様とご参拝の皆さんの中執持(なかとりもち)として励みたい」。
特別講話Special Interview
-
 ダイジェストムービー
ダイジェストムービー 
町とともにあり続ける御坊(ごぼう)として、人々が集う居場所に 稱念寺
住職/今井 慶子 師
-
 ダイジェストムービー
ダイジェストムービー 
地域産業や子供神楽(かぐら)を広める宇佐八幡ゆかりの氏神様 郡山八幡神社
宮司/上本 博之 氏
-
ダイジェストムービー

仏さまは誰一人見捨てない救いの存在 安養寺
住職/松島 靖朗 師
-
ダイジェストムービー

能楽の源流「翁舞」や樟の巨樹を、未来へ守り伝える 奈良豆比古神社
宮司/辰己 眞一 氏
-
ダイジェストムービー

人が集い自然に感謝することが神社の始まり 丹生川上神社上社
宮司/望月 康麿 氏
-
ダイジェストムービー

考え寄り添い、真に平等な社会の実現を 壷阪寺(南法華寺)
住職/常盤 勝範 師
-
ダイジェストムービー

思い煩(わずら)いをお預けし、ともに祈り、今できることを 金峯山寺
金峯山修験本宗 管長・総本山金峯山寺 管領/五條 良知 師
-
ダイジェストムービー

導きの神様を祀り、遍(あまね)く人々の幸せを願う 飛鳥坐神社
宮司/飛鳥 弘文 氏
-
ダイジェストムービー

奈良は歩き景色を眺め思いを馳せて祈る場所 八咫烏神社
宮司/栗野 義典 氏
-
ダイジェストムービー

伽藍復興と千三百年の想いを未来へ取り次ぐ 薬師寺
管主/加藤 朝胤 師
-
ダイジェストムービー

仏・法・僧を守り、かまどの 神を祭り、大自然とともに 荒神社(立里荒神)
禰宜/林 正裕 氏
-
ダイジェストムービー

皆で助け合い、 この世に調和の世界を作ること 當麻寺中之坊
院主/松村 實昭 師
-
ダイジェストムービー

私たち一人ひとりが お地蔵様となり良き世を 矢田寺(金剛山寺)
山主/前川 真澄 師
-
ダイジェストムービー

貴重な森や神楽を通し、 地域の歴史を伝える 村屋坐弥冨都比売神社
宮司/守屋 裕史 氏
-

自分を見つめ、助け合い、尊重と融和の日常へ 櫻本坊
住職/巽 良仁 師 神職/巽 安寿 氏
-

聖徳太子の「和」の心を明日香村から伝え続ける 橘寺
住職/髙内 良輯 師
-

世に調和をもたらす風を祀る 龍田大社
禰宜/稲熊 憲彦 氏
-

日々、全世界が仲良くあれと願って 中宮寺
門跡/日野西 光尊 師
-

神仏習合の社 大改修に向けて 玉置神社
宮司/舛谷 武 氏
-

時を越え伝える 聖徳太子の和の心 法隆寺
管長/古谷 正覚 師
-

憂いを手ばなし、見つめ直そう 墨坂神社
宮司/太田 静代 氏
-

学び知って、皆で未来を切り拓く 東大寺
別当/狭川 普文 師
-

美しい十一面観音と、どこかユーモラスな子安延命地蔵を祀る 聖林寺
住職/倉本 明佳
-

各時代の善知識(ぜんちしき)によって守られた古刹 法輪寺
住職/井ノ上 妙康
-

聖徳太子らも手を合わせた日本最初の寺院 飛鳥寺
住職/植島 寶照
-

『記紀』に記された、日本建国の地に鎮まる 橿原神宮
宮司/久保田 昌孝
-

草創1300年記念事業の続く西国三十三所観音巡礼の札所 岡寺
住職/川俣 海淳
-

「観光から信仰へ」をかかげる文殊菩薩の霊場 安倍文殊院
執事長/東 快應
-

南朝の歴史を伝える古刹 如意輪寺
住職/加島公信
-

明治天皇の御願により後醍醐天皇を祀る社 吉野神宮
宮司/東 輝明
-

光明皇后の慈悲の心を受け継ぐ尼寺 法華寺
門主/樋口 教香
-

平城宮とともに発展した古寺 海龍王寺
住職 /石川 重元
-

水と芸能の神 峯本宮 天河大辨財天社
宮司/柿坂神酒之祐
-

修験道の根本道場 龍泉寺
住職/岡田 悦雄
-

始まりの地、葛城と鴨族 高鴨神社
宮司/鈴鹿 義胤
-

庶民信仰とならまち 元興寺
住職 (公財)元興寺文化財研究所理事長 /辻村 泰善
-

聖徳太子と毘沙門信仰 信貴山朝護孫子寺
信貴山真言宗管長/総本山朝護孫子寺法主 田中 眞瑞
-

水を司る衣食住の守護神 廣瀬大社
宮司/樋口俊夫
-

現代に受け継ぐ寺子屋の学び 長弓寺 円生院
副住職/池尾 宥亮
-

女人高野と桂昌院 室生寺
大本山室生寺 座主/網代智明
-

叡尊上人と一味和合の精神 真言律宗総本山 西大寺
真言律宗管長/大矢實圓
-

鑑真和上がつなぐ懸け橋 律宗総本山 唐招提寺
長老/石田智圓
-

藤原鎌足と多武峰信仰 談山神社
宮司/長岡 千尋
-

祭祀の場と『古事記』 丹生川上神社(中社)
宮司/日下 康寬
-

青年・空海と奈良 南都七大寺 大安寺
貫主/河野 良文
-

日本最古の神宮とご神宝 石上神宮
宮司/森 正光
-

中金堂を含む天平空間の再興 法相宗大本山 興福寺
貫首/多川俊映
-

仏教から見たおもてなしの心 法相宗大本山 薬師寺
法相宗管長/山田法胤
-

式年造替と、自然との共生 春日大社
宮司/花山院弘匡
-

和の精神と世界遺産 聖徳宗総本山法隆寺
管長/大野 玄妙
-

お参りの仕方とマナー 真言宗豊山派総本山長谷寺
法務執事/登坂高典
-

日本人の祈りの原点 大和一ノ宮三輪明神 大神神社
宮司/鈴木寛治
-

吉野の桜と修験道 金峯山修験本宗 総本山 金峯山寺
金峯山修験本宗 宗務総長/田中利典